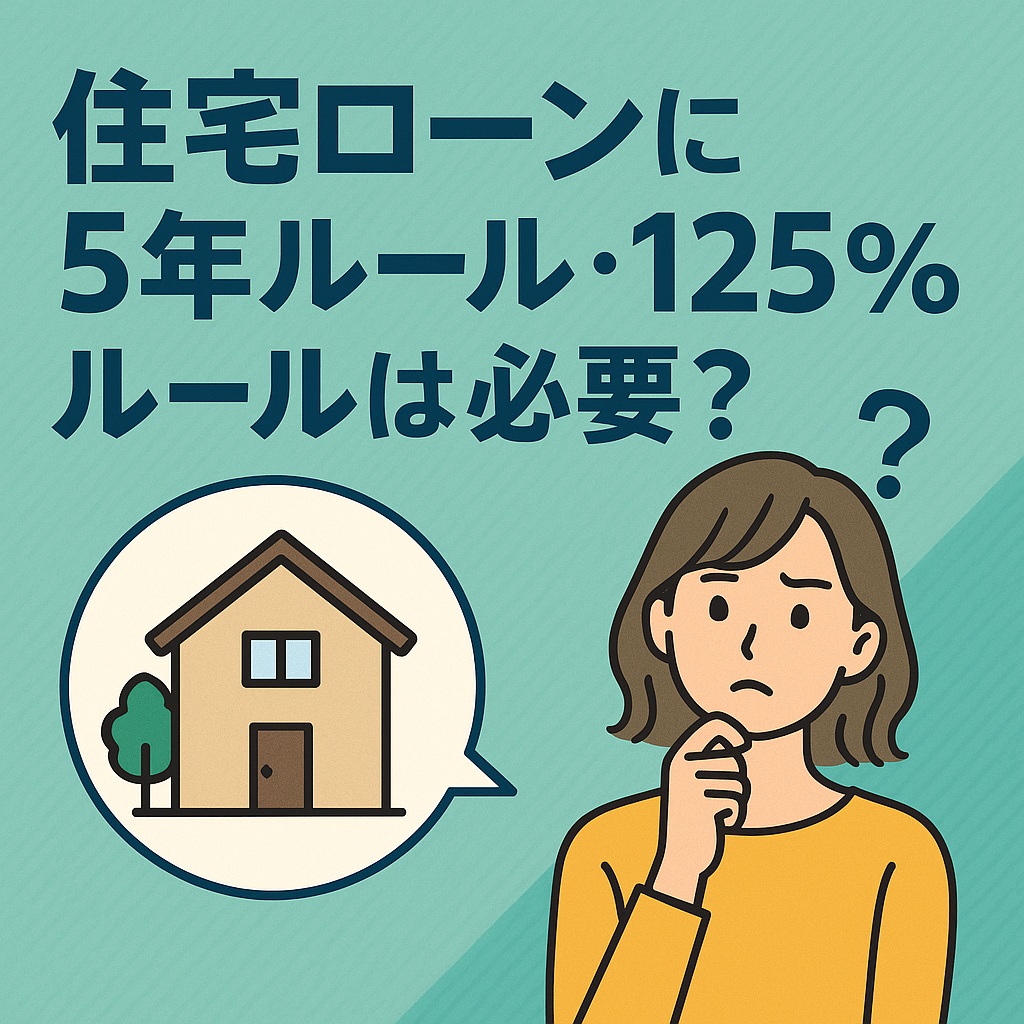 この記事では、金利上昇局面でも住宅ローン利用者の返済負担を緩和する機能がある「5年ルール・125%ルール」についてわかりやすく解説していきます。
この記事では、金利上昇局面でも住宅ローン利用者の返済負担を緩和する機能がある「5年ルール・125%ルール」についてわかりやすく解説していきます。
目次
住宅ローンの「5年ルール」と「125%ルール」とは?その仕組みと注意点を徹底解説
住宅ローンで変動金利型を選択した場合、一般的には半年ごとに金利の見直しが行われます。つまり、金利が上昇すればローンの返済額も増加するリスクがあります。一般的に、金利が上がったからといって、すぐに毎月の返済額が増えるわけではありません。
その理由は、多くの金融機関が「5年ルール」や「125%ルール」という仕組みを設けているからです。これらのルールにより、急激な返済額の増加が抑えられる仕組みが導入されています。
5年ルールとは?
「5年ルール」は、金利が上昇しても最初の5年間は毎月の返済額を据え置くルールです。仮に借入当初の金利が低く、その後金利が上昇した場合でも、すぐに返済額が跳ね上がる心配はありません。これにより、家計に急激な負担がかかるのを避けることができ、家計管理の見通しを立てやすくなります。
125%ルールとは?
「125%ルール」は、5年ルールが適用された後の6年目以降の返済額の上限を定めたものです。具体的には、前回の返済額の125%を超えて増額しないというルールです。たとえば、毎月の返済額が10万円だった場合、6年目以降に金利が上昇しても最大返済額は12万5,000円までに抑えられます。
この仕組みは、金利上昇局面においても返済額の急激な増加を防ぎ、家計の安定性を保つためのセーフティネットといえます。
5年ルール・125%ルールのメリット
5年ルールと125%ルールの最大のメリットは、金利が上昇した場合でも、毎月の返済額が急激に増えるのを一時的に抑えられる点にあります。教育費や住宅の維持費など、家計の支出が重なりやすい時期であっても、返済額が5年間は原則として据え置かれるため、見通しを立てやすい資金計画を組むことができます。
また、6年目以降の返済額についても、増加幅が直前の返済額の125%までに制限されるため、返済額が短期間で大幅に跳ね上がるリスクを避けやすくなります。この仕組みは、子育て世帯や共働き世帯など、長期的な家計管理を重視する方にとって、将来の不確実性に備えるうえで心強い安心材料と言えるでしょう。
5年ルール・125%ルールのデメリットと落とし穴
一方で、これらのルールには見落としがちなデメリットもあります。まず注意したいのは、返済額の増加が抑えられる一方で、金利上昇分の未払い利息がローンの元本に繰り越される可能性がある点というです。
つまり、5年ルールや125%ルールによって一時的に返済額が抑えられても、未払い分を後回しにされ最終的にはローン残高が増加することもあり得るというわけです。その結果、ローン完済時に予想外の一括返済が求められるケースや、返済期間の延長、追加利息の負担が発生するリスクも考えられます。
さらに、125%ルールは「返済額の増加ペースを緩やかにする」ものであり、総返済額そのものを減らす仕組みではないという点も理解が必要です。金利が上昇する局面では、表面上の返済額が安定していても、長期的には返済総額が膨らんでいく可能性があります。
「125%ルールは意味がない?」その誤解を解説
そういったデメリットを考えて、「125%ルールは結局あまり意味がないのでは?」という声もあります。確かに、仮に初期金利が0.5%の住宅ローンで、金利が2.0%程度まで上昇しなければ、125%ルールの適用には至りません。そもそも大幅な金利上昇がなければこのルールは発動しない仕組みであるため、金利が安定している局面ではこのルールが「無意味」に見えるのです。
しかし、このルールの目的は、「万が一の金利急上昇リスクから借り手を守る」ということにあります。平時には出番がないものの、金利が急騰している時には重要な役割を果たします。いわば、保険的な性質を持つルールといえるでしょう。
5年ルール・125%ルール採用型 vs 非採用型ローンの比較
最近では、5年ルールや125%ルールを採用していない変動金利型住宅ローンを提供する金融機関もあります。このタイプのローンでは、金利上昇があった場合、すぐに返済額に反映されるため、金利上昇局面では返済額が急増するリスクがあります。
ただし、裏を返せば「未払い分が後回しにならない」という特徴もあります。将来に未払い金が積み上がらない分、ローン終盤に一括返済を求められるリスクを回避できるという見方もできます。
どちらのタイプが優れているかは一概には言えず、借りる人自身のリスク許容度や家計状況、ライフプランに応じた選択が重要です。
最適な住宅ローン選びのために
変動金利の住宅ローンのリスクを軽減する方法としては、固定金利への借り換えも有効です。固定金利は金利上昇リスクを回避できる一方で、変動金利よりも初期金利が高い傾向にあるため、市場の金利動向や将来の収入見通しを加味して検討することが求められます。
また、金融機関によって「5年ルール」「125%ルール」の詳細や適用条件が異なる場合があるため、契約前には商品概要説明書や担当者への確認を徹底することが重要です。
住宅ローンは、単なる「金利の安さ」だけでなく、返済のしやすさ・将来的なリスク・家計への影響といった多角的な視点で選ぶことが、後悔しない住宅ローン選びにつながります。
